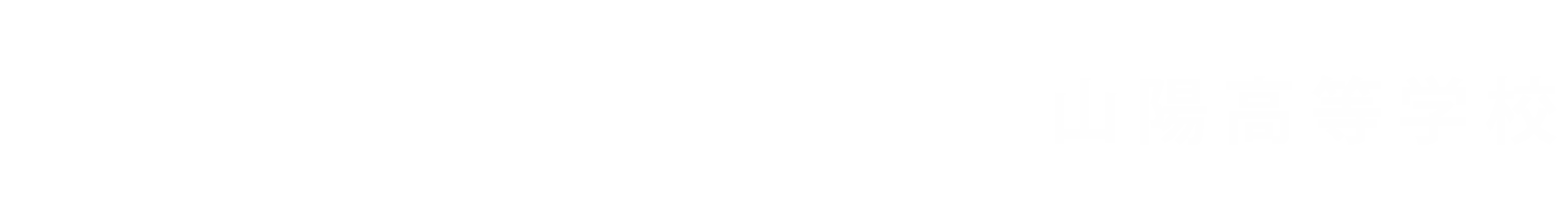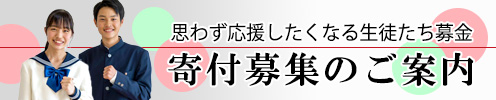ヴィルヘルム・ミュラー
(1794~1827 Johann Ludwig Wilhelm Müller )
今回は、本校卒業生の今田陽次さんのバリトン独唱をご紹介致します。高度な歌唱力を必要とするドイツ歌曲(リート)を今田さんの歌声とともにお聞き下さい。
「冬の旅」を作詞したヴィルヘルム・ミュラーはシナゴーグ(ユダヤ人の会堂)やキリスト教会といったさまざまな宗教建物が立ち並ぶアンハルト・デッサウ公国(現在はドイツ)に職人の息子として生まれました。デッサウは啓蒙思想が盛んな都市でした。
「冬の旅」は24曲で構成されたシューベルトによるドイツ歌曲(リート)で、今回はこの中から数曲を選び、ドイツを代表するロマン派の画家カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ(1774~1840 Caspar David Friedrich)の絵画とともにご紹介します。
17世紀の頃のドイツは、今のような1つの国家ではなく、神聖ローマ帝国を構成する領邦国家のひとつにすぎませんでした。1805年、神聖ローマ帝国はナポレオンによって解体されました。
第1曲目 「おやすみ」 (曲名をクリック)
「おやすみ」は夜、旅人がいとしい人を眠りから起こさないようにそっと旅立つ場面から始まります。
「おやすみ」
ひとり旅のよそ者としてここを訪れたが
またひとりよそ者としてここを去っていく
花咲く季節には数々の花束を編んで
贈り物にしたものだった
かつて5月は私をやさしく迎えてくれた
たくさんの花束とともに
彼女は僕を好きといってくれたし
その母親は結婚をすすめてくれたのに
それが今は灰色の冬景色となり
歩む道も雪の下に隠れてしまった私には旅立つ時を
選ぶことはできず
ひとり暗い夜道を
たどっていくのだ
月影だけがいつまでも
ぼくについてくるだろう
そして一面の雪野原を行くときは
獣の足跡を道がわりにたどって行こうもうこれ以上とどまれはしない
みんなが白い眼で見ているのだから
家の前につながれた犬ですら
ぼくを見て狂ったように吠え立てる
恋はさまようことが好きだ
つぎからつぎへと絶え間なく
神がそう定めたのだ
それではおやすみ、いとしいひと!きみの夢をさまたげぬよう
きみのまどろみを破らぬよう
足音をしのばせ、気を配って
そっと そっと戸を閉めよう
そして門を出るときにその柱へ
きみのために「おやすみ」と書きつける
それできみがわかるように
ぼくの変わらぬ心のうちを
旅人は”ひとりよそ者(fremd)としてここに来て、ひとりよそ者(fremd)としてここから去ります。
ここで使われるfremdは「よその/他人の/見なれぬ/異質な」などの意味を持つ形容詞ですが、名詞的に使われることが多く「自分自身の国にいながら居場所がない」といったニュアンスをもちます。
「冬の旅」全体に流れるさすらいの心情は、かつての神聖ローマ帝国にいた人々にとって共鳴する感情でした。

カスパー・ダーフィト・フリードリヒ『冬』(1807-1808)
3曲目 「凍った涙」 (曲名をクリック)
「凍った涙」
凍ったしずくがこぼれる
僕の両頬を伝って。
何ということだ、知らぬ間に
ぼくは泣いていたのだ。ああ、涙よ、流れる涙よ
なんてぬるい涙
それではすぐ凍ってしまうわけだ
冷たい朝露のように。だから胸からほとばしり出よ
熱く、たぎる思いが。
この冬をすべておおうすべての氷を
融かし去ってしまうほどに!
ミュラーは「胸からほとばしり出た」涙は「熱くたぎる思いで、すべての氷を融かしさってしまうほど」といいながら、その涙は「ぬるいのですぐに凍ってしまう」と自嘲します。
ドイツ解放の戦いに参加するために大学を中退したミュラーは義勇兵を志願してフランス軍と戦いました。ナポレオン軍とロシア・プロイセン同盟軍との戦いは熾烈を極め、両軍あわせて連日1万人の兵士が命を落とし、バウツィエンの兵には敵味方の区別なく至るところに戦没者が埋葬されました。
「「冬の旅」は私たちに過ぎ去った戦争を思わせる一方で、凍りついた平和をも思わせるのである。」

カスパー・ダーフィト・フリードリヒ『冬景色』(1807-1808)
5曲目 「菩提樹」 (曲名をクリック)
「菩提樹」はシューベルトの連作歌曲の中で、もっとも単独で歌われることの多い曲です。
4曲目「氷結」の終わりのせわしない鼓動の音はやがて「菩提樹」の枝のざわめきへと変化します。
「菩提樹」
市門の近くの噴水のそばに
1本の菩提樹が茂っている
僕はその涼しい樹陰で
いく度も甘い夢に耽(ふけ)ったもんだぼくは幹に刻んだ
数々の愛の言葉を
嬉しい時も悲しい時も
いつでもその木に引き寄せられただが今もまた旅ゆくさだめ
夜更けてそこを通りかかり
暗闇の中でそっと
目を閉じたすると菩提樹の枝がざわざわと音を立てる
ぼくに呼びかけるように
おいで お若いの
おまえの安らぎの場はここだよ冷たい風が真っこうから
顔に吹きつけ
頭から帽子が飛んだが
ぼくは振り向かなかった今やあの場所から
遠く離れたところにいるのに
ざわざわという音がずっと耳に残っている
おまえの安息の場はあそこなのにと
菩提樹は落葉樹ですが、ここに出てくる菩提樹は“真冬にもかかわらず緑豊かな菩提樹”です。
中世の頃よりドイツの菩提樹は「民衆集会の木」や「裁きの木」として知られており、憩いの場とともに「生」と「死」の神託が行われる場所でもありました。
この頃のドイツの冬は今よりもはるかに寒く厳しく、冬の菩提樹の下で眠ることは「死」を意味します。ミュラーの詩には幾度も「死の誘惑」が登場しますが、旅人は一貫してそこから遠ざかろうとします。ロマン主義の時代(音楽のロマン派は文学のそれよりも1世紀後にきたのですが)、人々はおそらく戦争体験によって「死こそが安息をもたらし、生こそが苦難である」という考え方が文学や芸術など多くの分野にみられるようになりました。
「おいで お若いの、お前のやすらぎの場はここだよ。」
旅人はかつて自分が愛を刻み、安息をもたらしてくれた緑豊かな菩提樹を想起しますが、それは幻想です。旅人は目をつむり、強風に帽子が吹きとばされようと振り返らずに菩提樹を通り過ぎます。
「おいで 安息の場はあそこなのに。」
それは社会的な偽善、精神的な救済の構造としての菩提樹を捨て去る旅であった。どこまで歩いて逃れようとしても圧迫してくる菩提樹を捨て去ることは、すなわち幻想を捨て続ける旅であった。
あらゆる幻想-具体的には信仰・権威・共同体からのお仕着せ等々-を拒否し、そこから逃れる。これは不可能性の追求と言っていい旅であろう。
ヴィルヘルム・ミュラーの生涯
渡辺美奈子
東北大学出版会

カスパー・ダーフィト・フリードリヒ『森の中の追撃兵』(1814)
~森に迷い込んだ追撃兵の死をカラスが待っています~
21曲目 宿屋 (曲名をクリック)
「宿屋」
ぼくの歩む道はいつしか
とある墓地に達した。
ここにこそ宿りたいもの
と、ぼくはひとり想った。墓にかけられた緑の葉の環よ
おまえたちは疲れはてた旅人に
墓という冷たい宿を示す
看板を意味するのだろうかそれでひとつたずねるが
部屋はまだ空いているだろうか
ぼくは今にも倒れそうなのだ
死ぬほどひどく傷ついてああ、このつれない宿屋よ
こんなに頼んでもだめなのか
それではさらに先をいくばかり
この忠実な杖を頼りとして!

カスパー・ダーフィト・フリードリヒ『樫の森の修道院』
「緑の花輪」は葉や枝を輪に編み死者に贈るものですが、居酒屋の入口にもおかれていました。ドイツでは中世の頃から「悪魔の宿屋」は「あの世にわたる境界地にある」という言い伝えもあり、シューベルトは「宿屋」に葬送曲を用いることで宿屋を墓場と見立てています。そこは既に一杯で入れないのです。
『冬の旅』のこの時点で、私たちは墓に入る。これは芸術が達成しうるもっとも陰鬱で本質的な対峙であり、このツィクルスのなかでは「霜おく頭」という曲で繰り返された「棺に入るまであとどれくらいあるのだろう!」というあいまいな質問であらかじめ示されていた対峙(たいじ)でもある。(中略)
(この想像の)世界では、旅人は「宿屋」を聴いているひとりひとりの観客が、空想上の墓と化してしまい、彼はそのなかに入りたいと強く願うのだ。 しかしそれは出来ない話である。
この曲は、最初の曲に勇ましくも戻っていくことで終わる。その勇ましさは次の曲への虚勢へとなりかわっていく。
シューベルト「冬の旅」
イアン・ボストリッジ
ARTES
「冬の旅」の連作歌曲において、シューベルトはミュラーのツィクルスの順番を入れ替えています。
シューベルトが23番目に選曲した「幻の太陽」には「宿屋」と同様に讃美歌のような曲が使われています。シューベルトは「幻の太陽」を、「断固として神はいない」といいきった「勇気」と隣り合わせに並べることで、「生きているものと、生きているように見えるにすぎないもの」から神秘性を取り除き、理性的に捉えようとする時代の到来を示しました。
24曲目 手琴(ライアー)弾き(マン) (曲名をクリック)

手琴(ライアー)弾き(マン)
むこうの村はずれに
辻音楽師がたっている、
そしてかじかんだ手で
手琴を奏でている素足のまま氷の上を
よろめき歩いている
そして小さな受け皿には
一銭も金が入っていない誰ひとり聴くものはなく
彼を見るものはいない
そして犬どもだけが
老人のまわりをうろついているまわり全てのことに
全く無関心のまま
いつまでも手琴を奏でて
音の止むことはないなんと変わった老人か、
おまえについていこうか、
おまえはぼくの歌に合わせて
その手琴を奏でてはくれないか
「冬の旅」最後の曲です。抒情詩はもともと竪琴(たてごと)に合わせて歌われるものでしたが、この老人は社会で最下層の物乞いが奏でる「ハーティ=ガーティ」とよばれる楽器を演奏しています。
「おまえはぼくの歌に合わせてその手琴を奏でてはくれまいか。」
今田さんの歌曲を聴くと、旅人を表す「声のパート」と手琴弾きを表す「ピアノ・パート」がゆっくりと、徐々に近づき、ともに歩み始め、後半ではピアノが旅人を誘導するかのような演奏へと変化していくことが分かります。
作家ミュラーの恵まれない人々に対する思いやりは作品の中でたびたび出てきます。貧しい者に対する博愛の精神は故郷デッサウでの汎愛的教育によるものであったと考えられます。手琴弾きにみた「ありのままの姿」「周りのすべてに無関心であること」。その姿をみた旅人はやがて「苦しい現実社会に止まり続けること」を選びます。
本校卒業生の今田陽次さんはドイツ・リートを「“歌う”というより“語る”」と表現し、ピアニストと声楽家と聴衆とが三位一体となったときに会場が輝くように見え、音が形となって届いたことを実感するそうです。ピアノ伴奏は今田さんの歌と歩むように、語りかけるように演奏されます。
かつてシューベルトが仲間らと演奏をしていた小さな室内楽「シューベルティアーデ」は今なおオーストリアの山間で行われ、シューベルトを偲んで世界中から多くの著名な音楽家たちが集まります。
<オーストリアのシューベルティアーデ>
https://www.austria.info/jp/things-to-do/music-and-art/festivals-in-austria/schubertiade

ユリウス・シュミット『シューベルティアーデ』(1896)
シューベルトはミュラーをはじめ、ゲーテやシラーといった抒情詩に好んで作曲をしました。そしてミュラーの詩は、シューベルトの作曲によって「水車小屋の娘」とともにドイツ歌曲(リート)の代表的作品となりました。かつて、教会の権威であった宮廷音楽はピアノの普及によって室内楽を可能とし、抒情詩と繋がることで情緒的で表現力豊かな音楽になりました。「魔王」「鱒」に代表されるシューベルトは、古典派とロマン派のはざまにありながらも常に新しい演奏の形を追い求めました。シューベルトは卓越した才能に恵まれながらも31歳の若さで亡くなりました。既にこの時病魔におかされていたシューベルトは、「冬の旅」全体を覆うさすらいの風景の中に、自由のない抑圧された時代からの解放と、自らの心情を重ね合わせていたのかも知れません。